| |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
 | ||||||||||
| ガードをくぐると水戸海道と合流。(写真左上) 古隅田川に沿った道なのでかなり曲がりくねって いる所から大曲と呼ばれていたところです。 道なりに常磐線から離れる方向に進むと 新しくできた広い道に合流しますが、良く探すと 古いたたずまいの家も見られます。(写真右上)  さらに進むと曳舟古上水橋の碑(写真上)があり、 曳舟川親水公園になっています。 ここには新しく建てられた「これより水戸佐倉街道」 や「亀有上宿」の石碑がありました。(写真右) |
| ||||||||||
 |
 | ||||||||||
| 亀有は千住宿から一里で新しい七福神と一里塚が建てられていました。(写真左上) 実際の一里塚は、中川方向に10mほど先にあったそうです。 亀有上宿商店会が地域の発展を願い守り神として七福神を祀ったそうで街道筋に 見られますから探してみるのも良いでしょう。 でも、亀有と言えば「両さん」でしょうか。旧水戸街道にも「ワハハ両さん」がありました。(写真右上) | |||||||||||
 |
 | ||||||||||
| 環七の交差点ではアリオ亀有が見えてきます。(写真左上)さらに進むと中川があります。 現在は中川橋を渡りますが、江戸時代の終わりは「新宿の渡し」で渡りました。 今も新宿側の橋のたもとに船宿がありそばには小舟が繋がれていました。(写真右上) | |||||||||||
| |||||||||||
 |
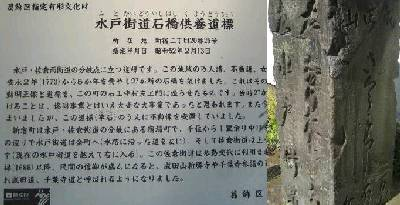 最近まで6号線との合流点のそば屋の脇には安永2年 (1773年)建立の「左水戸街道、右なりたちば寺道」と 刻まれた石造道標が残されていましたが、現在は 葛飾区郷土と天文の博物館で保存されているそう ですが公開はされていません。(2010年6月現在) じつはこのことを調べるためにこの博物館に行って、 葛飾古道図という展示を見て、新宿から流山古道が 出ているということを発見しました。 ならばここから先流山道を通った可能性の方が高い のではないかと言うことです。そちらについては後日 ルート調査をしたいと思います。 | ||||||||||
| 下宿に入る「かねんて」の奥に「日枝神社」が 祀られていました。 屋根が付いている珍しい形の鳥居でした。 (写真上) | |||||||||||
 |
 | ||||||||||
| 旧水戸街道は国道に合流したら直ぐの次の角を左折します。(左上の写真の木曽路の手前の広い道) 拡幅整備された道を進むと三叉路(写真右上)に出るので右へ進むと松の下に石仏等がありました。 | |||||||||||
 |
 | ||||||||||
| これは、新宿4丁目から移された13体の石仏石碑、帝釈道の道標(右端)だそうです。 | |||||||||||
 |
 | ||||||||||
| 少し行くと新小岩繰と金町間約7kmを結ぶ貨物支線新金線の浜街道踏切(写真左上)を渡ります。 水戸街道の別名を陸前浜街道と呼んだことから付けられた踏切名でしょうか。 細い直線道路を道なりに進むと右カーブして国道6号に合流しそうになります。 (写真右上) | |||||||||||
 |
 | ||||||||||
| 国道に沿って通る狭い路地があります。蛇行する道に小さな商店が並ぶいわゆる商店街らしい歴史を感じます。 栄通り商店街をぬけると京成金町駅の手前の踏切(写真左上)を渡ったら左折していったんJR金町方向に進むと 右の方にヴィナシス金町の所に6号線に抜ける道があります。 ここにはなんとなく古そうな店がありました。(写真右上) | |||||||||||
 |
 | ||||||||||
| さて正面に再び6号線が見えてきて(写真左上)合流します。 JR常磐線のガードをくぐり100m弱進むと右斜めに葛西神社に向かう道があります。 その道を進んで行くと岩槻街道との交差点付近に石碑がありました。(写真右上) 目の前には葛西神社の森が見えています。 | |||||||||||
 |
 | ||||||||||
| 葛西神社(写真左上)の創建は元暦2年(1185)下総国香取神宮の分霊を祀り葛西33郷の総鎮守と されたそうです。神社の前の道を進むと古い雰囲気の家(写真左上)やお寺などがありました。 | |||||||||||
 |
 | ||||||||||
| 道は江戸川に沿って北上します。(写真左)周辺には古い農家も点在しています。 やがて外環道の葛飾大橋、旧道の旧葛飾橋をくぐり東京都下水道局金町ポンプ所に出ます。 ここが古道「水戸海道」の都内側の終着「金町関所跡」の新しい石碑(写真右上)が建てられています。 | |||||||||||
 |
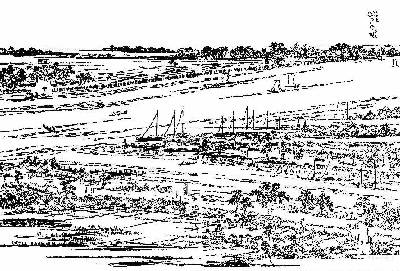 松戸側から見た金町方向今(写真)昔(絵) | ||||||||||
 |
 | ||||||||||
| 松戸の渡しを渡し船で江戸川を渡った旅人は下横町に上がりました。 ここからが松戸宿で現在は新しい碑(写真左上)が建っています。 渡船場道を直進する(写真右上)と旧街道に出ますがこのあたりは渡船場河岸(下河岸)とよばれ、 銚子から利根川をさかのぼってきた鮮魚をあつかう魚市場で賑わった場所です。 松戸宿には本陣1軒、脇本陣1軒、旅籠28軒の規模で石碑の場所から旧水戸街道辺りが松戸宿の 中心地でした。本陣(松戸郵便局あたりにあったようです)・脇本陣・問屋場・高札場等がありました。 | |||||||||||
 |
 | ||||||||||
 |
 | ||||||||||
| 松戸旧街道沿いには古いたたずまいの建物が今もあちこちに残り松戸宿の名残も残る。 | |||||||||||
 |
 | ||||||||||
| 松戸宿を抜け根本交差点で水戸海道から左に分かれ現在流山街道と呼ばれている道に入るとすぐに 坂川(写真左上)を渡り京成自動車の松戸車庫(写真右上)の横を通る。古ヶ崎五叉路という信号で 西口消防署の前の道を進む。こちらが流山古道だ。 | |||||||||||
 |
子育て地蔵(写真左)をはじめ庚申塔やお寺や神社 など(写真下)古道ならではの建造物が、次々と現れ てくる。 かつて松戸三郷有料橋だった橋の下を進むと江戸川 にぶつかる。 土手沿いの道が流山古道。 農家が点在する道を北上する。 この道は流山の職場に通勤で通っていた道だ。 まさかその道が流山古道だとは当時は少しも思わな かった。 | ||||||||||
 | |||||||||||
| 道なりに走ると右手に松戸生コンの建物が見えてくる。(写真左下) 走ってきた道はやがてほぼ直角にカーブし、横六間川に沿って走り100mほどでて流山街道に合流するが、 カーブして10mほどで土手沿いに走る道がある。(写真右下) 車1台やっと通れる狭い道だがこれが流山古道だ。 | |||||||||||
 |
 | ||||||||||
| 車が走る流山街道からは想像できないくらいローカルな色合いの濃い道を北に進む。 やがて主水池(もんといけ)が進行方向左側、江戸川の土手との間に見えてくる。(写真左下) ふだんから釣りしている人の多い場所だ。地元の人は「まこも池」と呼んでいるようだ。 | |||||||||||
 |
 | ||||||||||
| のどかな道をさらに進むと正面に国交省松戸排水機場が見えてくる。坂川放水路と江戸川の水位を 調整する所だ。(写真右上) | |||||||||||
 |
 | ||||||||||
| 排水機場を過ぎると、用水路から食用蛙の声が聞こえた。(写真右上)なんとのどかなことか! 小さな交差点はまっすぐ進むのだが右の方に社が見えたのでちょっと寄り道。 稲荷神社には庚申塔や石仏(写真右上)もいくつかあり、横には主水新田の集会所の建物があった。 この道を反対方向の江戸川の土手に上がって良く無線をして遊んだ場所だったことに気づく。 | |||||||||||
 |
 | ||||||||||
| 寄り道から戻り北上すると右前方に2つの煙突が見えてくる。六和クリーンセンターだ。 手前の木がこんもりと茂っている所は稲荷大神。ここにも庚申塔(写真右上)があった。 | |||||||||||
 |
 | ||||||||||
| クリーンセンターの裏を抜けると松戸市から流山市に入る。筑波エクスプレスの鉄橋が見えてくる。(写真左上) つくばエクスプレスは、橋を渡ってすぐトンネルに潜るので交通量の多い流山街道の地下を抜けることになる。 道をさらにまっすぐ進むと正面に観音寺(写真右上)が現れる。 今回は観音寺前を左折、すぐ右折して香取神社方向に進んだが、このあたりの流山古道のルートが不明である。 | |||||||||||
 |
 | ||||||||||
| 香取神社(写真左上)は実に不思議な神社である。なぜならここの参道に咲くタンポポは白い色をしている。 ここの参道から外れると普通の黄色いタンポポなのである。これも何かの御利益か? 香取神社の前の道を道なりに進むと水道橋が見える。(写真右上) この写真は水道橋を通り過ぎて後ろをふり返って撮ったもの。中央の森のような所が香取神社である。 | |||||||||||
 |
 | ||||||||||
| 正面には武蔵野線のガードが見え流山橋の下をくぐり抜け500mほど進むと旧流山橋の橋桁だけが残って いる所がある。(写真左上)このあたりに三郷(二郷半)からの丹後の渡しがあったそうだ。 土手沿いを流山橋方向を眺めると古い家並みも望める。(写真右上) | |||||||||||
 |
 | ||||||||||
| 正面のこんもりした山が赤城神社。(写真左上)上流の赤城方面から流れてきた山という流山の由来となった 伝説のある山である。この手前に分隊が宿をとったとみられる流山寺(写真右上)がある。 | |||||||||||
 |
 | ||||||||||
| 流山寺のすぐ側には赤城神社(写真左上)があり、その隣にはやはり分隊が宿をとったと言われている 光明院(写真右上)がある。これは単なる予想だが、江戸方面から追いかけてくるだろう追っ手に備え 本隊(本陣)を守るために流山の南の入り口とも言えるこの場所に分隊を備えたのだろう。 まさか官軍が北の粕壁・越谷からやってくるとは思わなかったこととせっかく作った爆弾などの武器が 到着しなかったために戦いもせず投降となったのかもしれない。 | |||||||||||
 |
 | ||||||||||
| 市内には昔ながらの家も見られる。(写真右上) 流山での駐留は、本隊が酒造家長岡屋に宿をとったとみられている。 (長岡屋があったと思われる場所=写真右上) | |||||||||||
| ふるさと足立に戻る | |||||||||||





